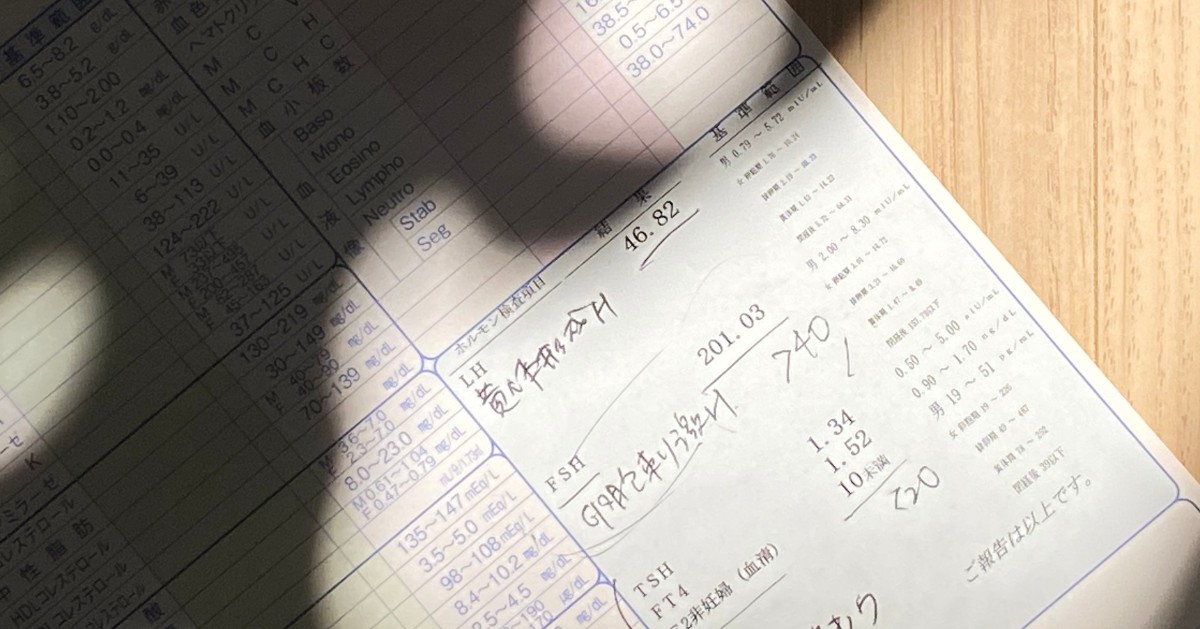だれかの写真で記憶と出合う

photo:yue arima
こんにちは。ライターの有馬ゆえです。
今年も、無事に5頭のアゲ子(アゲハチョウの幼虫)たちが旅立っていきました。うれしい。いや~、何回経験しても、驚くべき変態の様子に感動してしまいます。子どもが「自分はアゲ子のママ代わり」という自意識で接しているのも面白い。恐るべきお世話欲と感情移入。でもその気持ちわかる。現在、2ターン目の飼育中であります。

アゲ子さんとママさん。photo:yue arima
「行かない」子どもについて書いた前回のレターを配信して、何人かの方からメールを頂戴しました。集団になじまないお子さんを持った方からエール&情報提供をいただいたり、お子さんがすでに社会人になった方が子育てで感じたことを綴ってくださったり。ひとりぼっちのように錯覚していたけれど、そうじゃなかった~!と思えて心強かったです。ありがとうございました。
さて今回は、子どもと写真展を観に行って考えたことを書きました。ある日のセレンディピティについて。
セレンディピティ=偶然と偶然と才気によって、予期しない発見をすること(「TOPコレクション セレンディピティ」パンフレット)。
5月のある日、子どもが学校に行かないというので、恵比寿のアトレに入っているエコストアへ洗剤を買いにいった。屋上で昼食に私はサンドイッチ、子はでかい食パンを食べて、せっかくだからと東京都写真美術館の「TOPコレクション セレンディピティ 日常のなかの予期せぬ素敵な発見」を観に行った。
「セレンディピティ」。そのタイトルを初めてチラシで見た瞬間、わっと心が沸き立った。子どもと暮らし始めてから私の世界にもたらされてきたものについて、言い当てられたような気がしたからだ。そのときから、できたら子どもと行きたいなあと思っていたのだった。
子どもとは何回か一緒に美術館を訪れているが、とにかく我が子は作品を見るスピードが早い。興味のあるものだけに吸い寄せられて歩く姿は、花から花へと飛び回るみつばちのようだ。最近は「お母さんと美術館見てると遅くていやだ」とも言われていて、今回もさっさか展示室を出るのだろう、でもまあいいか、という気持ちでいた。
平日の午後いちばんの写真美術館は空いていて、私たちの他は旅行で日本に来たらしきバックパックの若い外国人カップルと、50代後半ぐらいのご夫婦らしき二人組がいただけだった。そのおかげで子どもは窮屈な思いをせずに済んだのかも知れない。意外とじっくりと鑑賞する我が子に驚いた。
走る犬を連続で撮影したアニメーションのような作品を眺めたり、中頃の人工芝の敷かれたゾーンで延々とクッションを並べ替えたり、奈良美智のイラストレーションと青い目のやせた白猫の組み写真を「好き」と言ったり。そんなふうに展示会場を自由に飛び回る子どもが足を止めたのは、出口近くに飾られた井上佐由紀「私は初めてみた光を覚えていない / I can’t recall my first light.」という作品だった。
本作は、この世に生まれ落ち、初めて目を開いた赤ちゃんの瞳を撮影した連作だ。そのなかでも我が子が引き寄せられたのは、まぶたがぎこちなく開いた赤ちゃんの顔を大写しにしたメインの3枚ではなく、その横にちょこんと展示された老人の顔をクローズアップした写真だった。
うるおいのない肌とこけた頬、透明なプラスチックの酸素マスク、それから少し濁った瞳と、その表面に差す一点の強い光。
キャプションを読むと、それが井上の祖父の写真であるらしい。祖父が寝たきりになってから亡くなるまでの2年間、井上はその瞳を撮り続け、それをきっかけに初めて光を見る赤子の目を見たいと考えて本作の撮影を始めたのだという。
たたずみ、死に向かう人の瞳をじっと見つめる子どものもとへ近づくと、
「じいじ思い出しちゃったよ」
と我が子はぽつりと言い落とした。
口元に酸素マスクが取り付けられていた、肉の落ちた父の顔を思い出す。
父が亡くなった日、タクシーで施設に到着したとき、彼はもうすでに命が切れるのを待っているような状態だった。夜が明けると、ベッドの真横にある大きな窓からは白く暖かい光が差し込んで、集まった私たち家族は押し黙って、ただ父が繰り返す呼吸の音だけを聞いていた。これが永遠に続くのではないかと思えるほどに、それはそれはおだやかな冬晴れの日だった。後から子どもに、あそこから父が回復し、また元気になると思っていたのだと聞いた。
そうか、君はあの光景を思い出したのか。
子どもは出口近くにあるアンケート用紙に、ほとんどひらがなでこのことを書いた。そして、受付のお姉さんに手渡しにいった。
2022年の夏の終わり、同じく東京都写真美術館へ「TOPコレクション メメント・モリと写真 死は何を照らし出すのか」を観にいったことを思い出した。
父の容態がどんどん悪化していたので「メメント・モリ」(ラテン語で「死を想え」)というタイトルにはやや気が滅入ったのだが、それよりも一人きりでたくさんの写真に囲まれたい、とチケットを買った。
一枚一枚の写真や絵をじっくりと観たり、キャプションや解説文のひとつひとつを丁寧に読んだするだけの元気はなく、ただなんとなく作品を眺めながら順路を追った。しかし最後の方で、知らず知らずのうちににすうっと目が吸い寄せられる作品群があった。
この空間に入って、ずっと静寂に浸っていたい。自分がここに居ることを許されている、そんな気持ちになる。作者は――と、確認して驚いた。
Josef Sudek。それは、大学で写真に没頭していたときに、他大学の写真部にいた年上の女性から教えてもらった写真家の名前だった。1997年だったから、今から26年前だ。女性は、私と同じ写真部の先輩の知人で、個人的に会うことはなかったが、私たちは互いに作品を通して共鳴するものを感じていた、ということも思い出した。
作品目録を見る。Josef Sudekは「ヨゼフ・スデック」と読むらしい。大学時代、名前の読み方すらもわからないその写真家をインターネットで検索したものの、うまく情報をつかむことができなかった、ような気がする。だから、心の中で「ジョセフ・スーデク」とローマ字読みしていたのだった。
あの当時、スデックは日本ではそれほど知られていない写真家だったのだろう。画像検索などない時代だったため、スデックの作品を見てみたいと思った私は、アートやデザインの書籍を数多く取り扱っていた渋谷のパルコブックセンターに行って、その名を探した。しかし作品集は見つけられず、やっとそれを手に入れたのは、短期留学したパリで立ち寄った小さな本屋だった。A5ぐらいの簡易な写真集だったが、以来、それは私の大切な逃避先になった。
光と影が美しく細部まで柔らかく焼き出された作品群を見つめて、それから紙焼きの粒子の一粒一粒を愛でて、20歳前後の自分に思いをめぐらす。そして、私は自分の居場所を探すために写真を撮っていたのだな、と気がついた。
ポートレートでない限り、私は人や動物の映りこんだ写真を撮らなかった。静けさを求めていたのだ。当時の私はどうしようもなく孤独で、かなり切迫した精神状態にあった。騒がしい現実からの逃げ場を探していたから、好きだと思える光景を見つけ出すと懸命にシャッターを切り、暗室の赤い光の中で自分が切り取った長方形の景色に集中することが、心の安寧につながっていた。焼いた写真を並べてみていると、不思議と安心できた。
あの頃の私は、街をさまよって好きな光景をフィルムに焼き付けたり、好きな写真家の作品世界に没頭したり、作品を通して誰かと共感しあったりすることで、どうにか生き延びようとしてきたのかもしれない。
20年以上のときが経ち、私はスデックの写真の前で、過去の自分をそんなふうに見つめていた。
写真とは、どこかにあった現実を映し出したものだ。
だれかの記憶であり、いつかの記録。写真とはそんな芸術であり、だからこそ私たちはだれかの写真を通して自分の記憶と再び出合うのだろう。井上佐由紀がとらえた病床の祖父の瞳が子どもの喪失の記憶を呼び覚まし、戦争で片腕を失ったスデックの見つめた光景が私の過ぎ去りし孤独との戦いの日々を思い出させたように。
だれかの写真とともに迎えた記憶との邂逅は、また新しい記憶になる。だれかと一緒に自分の記憶を見つめたという記憶に。写真を通して自分の記憶をたどることは、どこか心強い。それが自分だけの記憶であるにも関わらず、思い起こした私たちは、決して一人ぼっちではないからだ。
子どもが次に祖父の死を想い、さみしさを噛みしめるとき、写真美術館に展示してあった「私は初めてみた光を覚えていない / I can’t recall my first light.」を思い出してほしい、と願う。どこかに自分と同じような場面を見た人がいて、自分と同じような気持ちを抱いたかもしれない、という想像は、きっと子どもを支えてくれると思うのだ。
<参考文献・ウェブサイト>
ご意見、ご感想、ご相談、ご指摘、雑談などあれば、このレターに返信するか、下記のアドレスまでお寄せください。どうぞみなさま、おだやかな週末を!
bonyari.scope@gmail.com
すでに登録済みの方は こちら