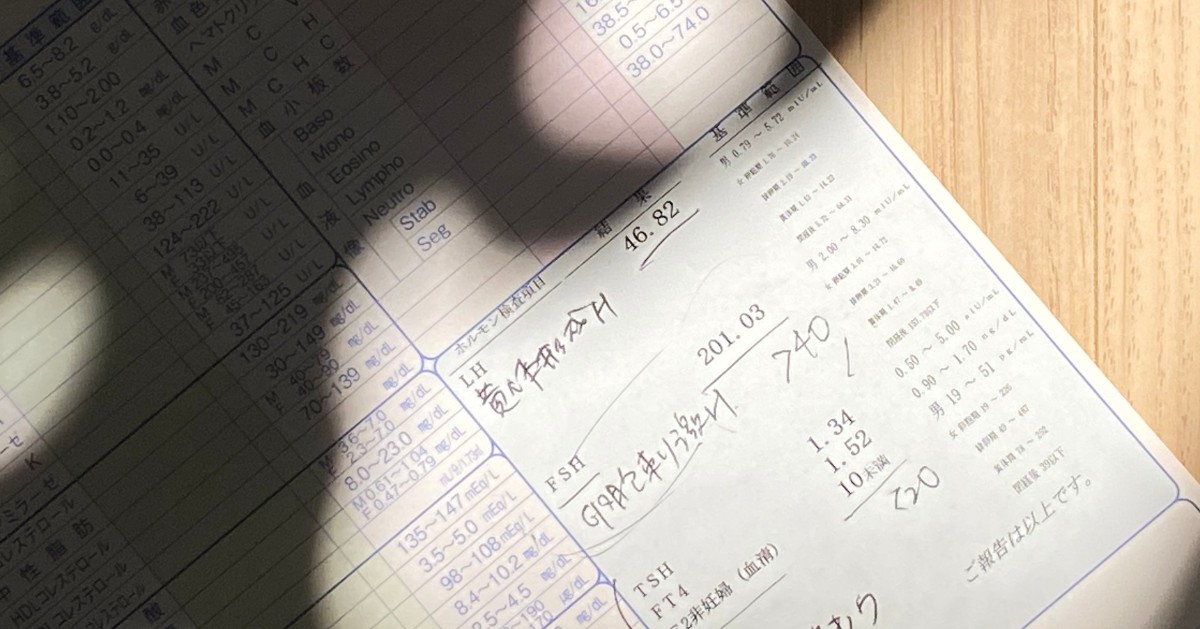しゃぼん玉があればなんとかなるのか

photo:yue arima
こんにちは。ライターの有馬ゆえです。
なかなかお便りできない間に、季節はすっかり秋。そしてキンモクセイの香り。私は子どもの馬跳びの練習に付き合って、太ももが数日間筋肉痛です。歩くと痛い。
さて今回は、しゃぼん玉にまつわるあれやこれやを。
あるとき、仕事部屋のプリンター棚の上に置いた小さな段ボール箱を整理することにした。これは子どもが赤ちゃんだった頃、普段はその手に届かない場所にしまっておきたいもの入れとして作ったボックスで、初めは年齢的にまだ早い鉛筆や消しゴム、おままごとセットから間引いたおもちゃの包丁などを入れていた。やがて育児が連綿と続くうち、それはたまにしか引っ張り出さないおもちゃの収納場所になり、子どもが小学校に上がると開けることもなくなっていた。
ほこりを払い、久しぶりに箱を開けてみて驚いた。60サイズの段ボールのほとんどを閉めていたのが、しゃぼん玉セットだったからだ。
多くは、星の模様がついたピンクの容器に黄色い蓋、吹き口は黄緑、というおなじみのあれである。確か、5本セットで税抜き100円。そうそう、私は100円ショップでしゃぼん玉をとにかく買ったのだった。ほかにも、吹き口の出口が五つに分かれていてひと吹きで複数個のしゃぼん玉が作れるもの、30センチほどのスティック状の容器に細長い楕円の吹き口が入ったもの、ハンドルをぐるぐる回すとイルカの口からわーっとしゃぼん玉が吹き出てくるもの、詰め替え用にしゃぼん液が入った500mlのボトル(これは300円)。いただきものの、魔法少女のスティックみたいなスイッチ一つでしゃぼん玉がわーっと出る電池式の物もある。
あの頃はしゃぼん玉があればなんとかなったな、と思った。
子どもが1歳ぐらいからだろうか、私はベビーカーのポケットには必ずジップバッグに入れたしゃぼん玉セットを忍ばせていた。飽きっぽい乳児の相手に疲れたときは「じゃじゃ~ん!」と取り出して、私が吹いたり、1歳の後半ぐらいからは子どもが吹いたり。お世話係としての生活に疲れ切っていたので、渡せばとにかく喜び、しばらくは間が持つしゃぼん玉セットは大変ありがたい存在だった。
3歳、4歳になっても、子どもはしゃぼん玉に飽きず、「どうぞ」と渡せばおもむろに片手のストローを吹いてしゃぼん玉を飛ばした。公園に行けばしゃぼん玉遊びをしている親子にしばしば遭遇するので、誰かが吹いたしゃぼん玉を追いかけたり、蚊を潰すようにして手でたたき割ったり、「きれ~」と眺めたりもしていた。
実際、20年ぶりぐらいでながめるしゃぼん玉は美しかった。特に晴れた日は最高だ。黄緑のストローをつまんでふーっと息を吹き込めば、光に縁取られたしゃぼん液が空気の振動を受けながら、静かに静かにふくらんでいく。震える表面にピンク、黄、青、紫の筋が伸び、かと思ったら縮んで右へ左へ移動して、ふっ、と、すきとおって濡れた球体になる。風に乗って、上下にゆらぎながら、遠くへ、遠くへ。
でもそんな美しい瞬間は、一時の夢であるとも言えた。
よく覚えているのは、子どもがストローに息を吹き込もうとするとき、容器を持つもう一方の手がお留守になってしゃぼん液が地面にバシャーとぶちまけられるシーンだ。そう、今の私なら「あらかわいいね~」としゃがんで子どもに笑いかけてしまうぐらいの愛おしモーメントである。
しかし私には、おおらかに見守る、などというのは文字にするほど簡単ではなかった。そうした失敗が起きるやいなや、耳の中で声が鳴り響くからだ。
「あーまたやった」「これスルーしちゃダメでしょ」「注意しないと」「ダメな大人になったらどうしよう」「騒ぎ始めたらめんどくさい」「もったいない」「しゃぼん液を無駄にしちゃだめって教えないと」「子どもの注意力を養わないと」「ちゃんとした大人になれないかも」――うるさくて、うるさくて、まともな判断なんかできずに、わーっと焦りがわいてくる。