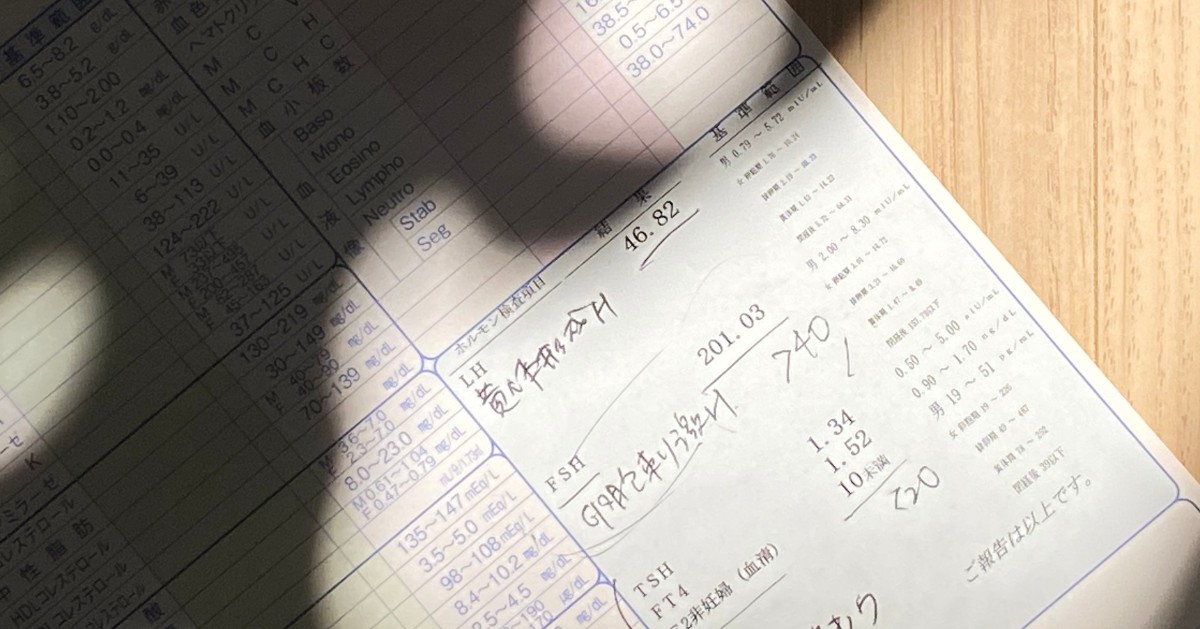いつか私を忘れた母の友だちになって
こんにちは。新しい月がやってきました。
最近の楽しみといえば、壁や舗道のすきまから伸びる雑草です。かわいいね、きみはここの花壇から飛んできたわけね、などとその姿を愛でつつ、生命力に恐ろしさを覚えたりもします。都会育ちの私にとって、植物とはああいう図々しさを携えたもので、それはそれは好ましい。住宅街の軒先花じっとり観察も日常茶飯事ですが、文字にすると危ないおばさんですね……。
さて今回は、「いつか私を忘れた母の友だちになって」と題し、本日70歳になった母について書きました。
母と別れる日をずっと恐れている。
母の死。自分の身体がひっぺがされるような感覚だ。母に忘れられたら、私のことを知っている人はいなくなる、そんな感覚がある。母の人生に私の記憶がなくなれば、私の人生の半分がなかったことになる。ような気がする。
母の死を意識し始めたのは、母が祖母の介護をしていたころだった。当時、祖母の記憶は少しずつはがれ落ちて、幼少期の話題――身体の弱かった祖母を養父がよく海水浴に連れて行ってくれたこと、いとこの子どもの年が近く妹のようにかわいがっていたこと、養子に入ったばかりの時期にだだっ広い部屋に一人で布団を敷いて寝るのが心細かったこと、庭に運転手さんの家があったこと、戦後に行き場をなくした兵士たちを養父が家にたくさん泊めていたこと――ばかりを口にするようになっていた。
それらは幼いときから聞かされたおなじみのエピソードだったけれど、祖母が一人の少女だったというのは到底、現実味のない話だった。むかしむかし、と語り出される物語のようで、目の裏ではなぜかモノクロ映画のように再現された。
だが祖母の少女時代は祖母にとっては現実で、彼女はいつしかその時代を生きるようになる。それを教えてくれたのは、母だった。
「おばあちゃん、小さいときに歌が大好きだったみたいでしょう? 気づくと、子どもみたいに童謡を口ずさんでることがあるの。すごくかわいいんだから」
祖母と毎日顔を合わせていた母が、ちょっとうれしそうに話したセリフをはっきりと覚えている。ピンクがかった白い花柄の綿のネグリジェを着て、ベッドに座った祖母の後ろ姿。すぼめた唇から流れ出る歌声。逆光のせいで、服の下のひどく曲がった背骨が浮かび上がっている。祖母は確かに同じ時代にいながら、私の知らない過去を生きている。まだ、母とも私とも出会っていない過去を。
そして思った。私もいつか、幼い母と出会わねばならないのだろうか。
幼い私を唯一覚えている母が、それをまだ知らない女の子になってしまったらどうすればいいのだろう。
二人で住んだアパートの光も、毎日朝食を食べたIKEAの白いダイニングテーブルも、二人でけんかして歩いたコリー犬のいる路地も、駒沢公園の回転するジャングルジムも、「パーラーができる」と期待していた店にパチンコ屋が入って二人で落胆したことも、私の中にしかなかったことになるのか。着ぐるみのキティちゃんに会って私が興奮してほほを赤く染めていたという母お気に入りのエピソードなんて、母だけしか知らないのに。考えるたび、かなしくてかなしくて涙が止まらない。
いつだったか、「安住紳一郎の日曜天国」(TBSラジオ)を聴いていたら、こんな投稿があった。
投稿者の女性の祖母は、孫娘であるその人のことを忘れてしまったという。しかし彼女は、ショックを受けつつも、祖母の地元の人として祖母と出会いなおしたのだそうだ。「あなたもあの街の出身なんですか? どのあたりにお住まいでした? あら、私と同じ町内だ。あそこの電気屋さん、ご存じ?」――なんて具合だろうか。祖母は自分の孫娘であるとも知らず、新しくできた地元の友人と過ごす時間を楽しんでいるらしい。そして、看護婦さんに彼女のことをうれしそうに話すのだ。女性は、こんなふうに続けていたように記憶している。
「きっと祖母はまた私のことを忘れてしまうでしょう。だけど、大丈夫です。また新しい友人として、祖母と出会い直せばいいのですから」
私も、いつか母と新たな関係を築けるだろうか。母が少女になったら、私は彼女とどう出会って、どんな友情を育もうか。母は、友人に恵まれなかったと聞く。母娘としての関係はいまもぎこちない私たちだけれど、一から友人関係を築いたら、うまくやれるだろうか。もし母と仲のいい友人になれたら、私は最後に大切な思い出を手に入れられるだろう。
取り壊された生家の話をしよう。彼女が小学5年生のときに建てられ、私が20歳まで過ごした二階建ての木造住宅。おじいちゃんが夕方になると水をまいていた、雑多で美しい庭。夕陽と、ホースのシャワーにたまに虹。薔薇や紫陽花、サツキ、シャクナゲ、チューリップ、テッポウユリ、桜草、アヤメや桔梗、ヒヤシンスにホタルブクロ。サルスベリと小さな八重桜も好きだった。小さな薔薇の木の下にある、母が小学生でつくった変な犬の置物が好きだった。グミの実はすっぱくて、鳥がたくさんついばみに来ていたね。トイレの窓から見えるドクダミの繁殖力に驚いた。毎夕、勝手口の横の井戸水の水道で、新聞屋さんが顔を洗って一口水を飲んだ。母はどんな思い出を語るだろう?
私は、そんなifも心待ちにする自分でいたい。母の最期、彼女の人生で一番の親友になれたらと想像して、自分を奮い立たせる。いつかの5月に、同じ月に生まれた者同士、一緒に誕生日会をできたらいいな。そのときは、私と母が幼いころに食べていた、あの洋菓子屋のバタークリームケーキにろうそくを差し、一緒にフーと吹き消そう。
すでに登録済みの方は こちら