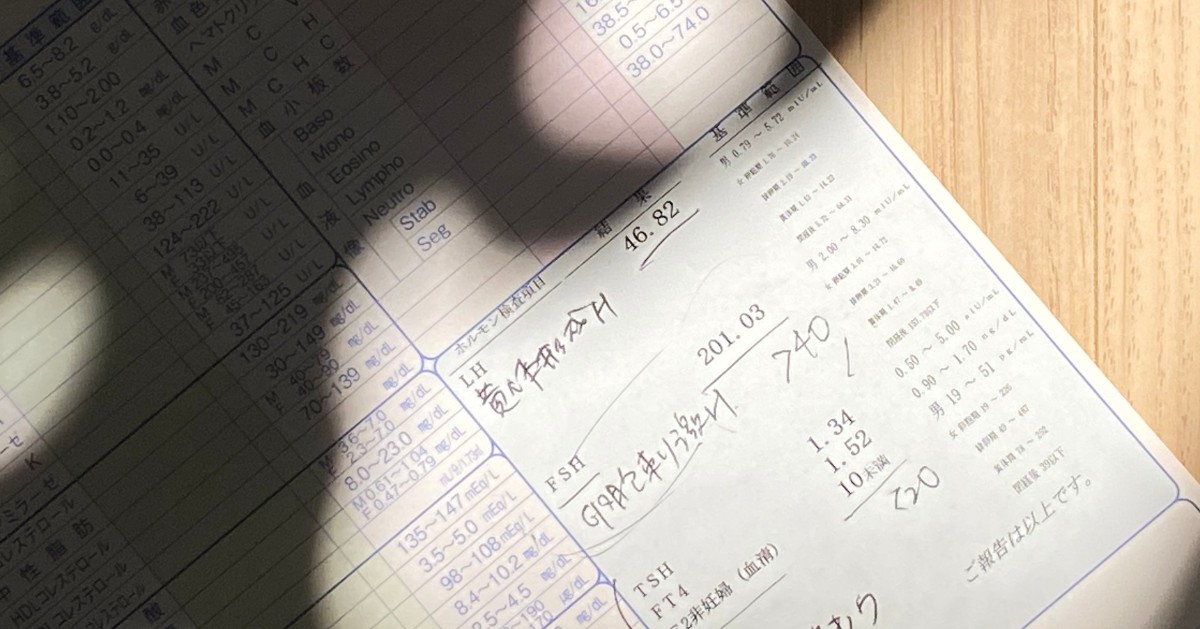メルちゃんのママ

うちの子のメル子。photo:yue arima
こんにちは。ライターの有馬ゆえです。
ついさっきストレッチポールに仰向けで乗って体を伸ばしていたら、キッチンでスプラトゥーンに励んでいた子どもが突然こちらに顔を向け、「そういうのもたいせつ!」と言い放ちました。人差し指まで立てて。うん、私もそう思う。
さて今回は、私が今の地域で気にかかっていた人たちについて。
出産を機に暮らし始めた2DKのマンションが手狭になったこともあり、暇さえあればウェブで物件をチェックする日々である。
引っ越し候補地の図書館や児童館、公園、学校などについて検索して新しい暮らしに思いを馳せていると、頭に浮かんでくるのは今住む地域で袖振り合った人たちのことだ。
例えば、近くの公園やバス停のベンチに出没する高齢の女性。根元が数センチ白い明るい茶のロングヘアーで、認知機能の低下のせいか的を数センチ外したような話し方をする。彼女は幼児をかわいがるのが好きなタイプのおばあちゃんで、うちの子どもも何度か家のそばの公園で一緒にダンゴムシやありの観察に付き合ってもらった。
忘れられないのは、ある夕方、息子らしい50代ぐらいの男性に叱られながら公園から帰って行っていった時の彼女の表情だ。なぜ叱られているのかわからないけれど、自分が過去にできたことをできなくなって迷惑をかけたことはどこかでわかっている。そんな心情をうかがわせる、おびえと深い悲しみをたたえていた。
それから、夫婦で「おっちゃん」と呼んでいるホームレスの男性。彼は近所の小さな雑木林のある公園の東屋にひっそりと暮らしていて、背中が前に35度ぐらい曲がっている。赤ちゃん連れの頃は危害を与えられたらと恐怖していたが、だんだん彼は彼の暮らしをしているだけだとわかるようになり、今度はやや心配して見守るようになった。夫も気にかけていると知ってからは、夫婦で彼の生存確認報告をし合っている。
おっちゃんは普段、図書館で本を読んだり、公園の水道で衣類を洗濯したり、食パンの耳を切って鳩に餌やりしたり、かと思えば折りたたみ自転車で我が家の前の坂を猛ダッシュしたりしている。しかしコロナ禍には半年以上、姿を見かけない時期もあった。三密回避のため黄色いビニールテープでぐるぐる巻きにされ、立ち入り禁止になった東屋を初めて見た時は、おっちゃんの命の心許なさを思い知らされた気がした。
どこかで生きていてほしいと傲慢に願ううち、ウイルスの存在はそのままに世間の雰囲気は緩み、私たちの日常とともにおっちゃんも東屋に戻ってきた。最近は、夫が東屋で洗濯物を干す彼を見かけたらしい。だが、その公園の一帯ではもうすぐ再開発工事が始まってしまう。そうなったら、彼はどこで風雨をしのぐのだろうか。
社会で「普通に」生きていくことは、簡単なようでとても難しい。今この瞬間、必死で紛れることができていても、たまたま不遇が二、三、積み重なれば、どんな人でもあっという間に社会の異物として扱われるようになる。彼ら、彼女らは、いつも私にそれを思い出させるのだった。
私がもっとも気持ちを寄せてきたのは、メルちゃんのママだ。彼女に初めて会ったのは、子どもがまだ赤ちゃんの時。昼寝している子どもを乗せたベビーカーを引っ張りながら自宅の前の坂道を慎重に下っていると、前方からキャップを目深にかぶった若い女性が同様にベビーカーを押して歩いてきた。
あ、ママさんだ、と体温が上がった。母親という責任の重い肩書きで社会を生きるようになって間もない頃、私はベビーカーを押す人を見かけると同志を見つけたようでうれしかったのだ。
しかしすれ違いざま、自然とベビーカーの中に視線を移しておののいた。中に寝ていたのが、乳幼児がお世話ごっこで使う人形「メルちゃん」だったからだ。メルちゃんは清潔で柔らかなタオルに大切にくるまれ、キラキラした目を開いたまま横たわっていた。
当時、私はちょうどお世話人形について執拗にネットで検索をしていて、このややギャルっぽい女児玩具的ピンク世界の住人「メルちゃん」が、日本のお世話人形界における二大巨頭の一人だということは知っていた。ちなみにもう一人はTHE日本の女の子という感じのちょっと目が怖い「ぽぽちゃん」で、この後ほどなくして段違いにかわいくおしゃんなディズニー系の「レミンちゃん」が登場する。
それから、私は彼女をマンションの前の坂道でたまに見かけるようになった。出会うのは必ず午後の時間帯で、メルちゃんをぎゅっと抱っこして出かけていくこともあれば、薬局でもらったらしきビニール袋を手に駅方面から帰ってきたこともあった。路傍でしゃがみ込んで泣いていたり、シートから薬を出して飲んでいたこともある。
彼女は病的に痩せていて色が白く、伸びっぱなしの髪の毛は黄ばんだ茶色をしていた。つば付きの帽子や洋服のフードを目深にかぶり、わずかに見える顔には生気が感じられない。寒い時期にはきれいめのコート、それ以外の季節でもビッグサイズのパーカーを洋服の上に必ず羽織り、下半身はグレーのスウェットやハーフパンツで足下は裸足にクロックスのサンダル。
彼女の様相には既視感があった。精神のバランスを崩して一人暮らしのアパートにこもりきりになった二十歳頃、私はまさに彼女と同じような姿をしていたのだ。
鬱状態に陥ってすぐ、寝ることも食べることもできずに私の体は、肉がそげ落ちて痩せ、ついでにアトピー性皮膚炎が悪化して湿疹だらけになった。外出はもっぱら精神科かコンビニで、お医者さんに話を聞いてもらわないとどうしようもない、薬やタバコがなくなってしまう恐怖に耐えられない、というギリギリの精神状態。羞恥心は残っているが見た目を整えるだけの力がないため、だるだるの部屋着の上に何かを羽織ってお茶を濁し、冬でも部屋で過ごしていた裸足のまま使い古しのサンダルを突っかけ、どうにかこうにか重たい体を玄関から引きずり出していた。
日中は人目や太陽光に責められているようでつらく、出かけられるのは夕方以降だった。それでも人目と電灯を避けたくて帽子を深々とかぶり、自分の心を守るため、メルちゃんの代わりにタバコケースを握りしめていた。MDプレイヤーのイヤホンを突っ込んで耳に爆音の音楽を流し込み、街の喧騒や幻聴を遮った。アパートから駅前にある病院までの300メートルほどの距離が何キロにも思え、たった一回の診療に出かけるだけでひどく疲労した。道ばたで涙が止まらなくなったり、一人きりで過呼吸になったことも何度もある。
だから私は、彼女は私だ、と思っていた。彼女もきっと、ギリギリで自分の生をつなぎ止めている。私とひとつだけ違うのは、その傍らによく母親が寄り添っていたことだ。母親は常に心配そうな表情をして、娘と一緒にしゃがみ込んだり、その背中をさすったりしていた。うらやましい光景だった。
視界に彼女を確認すると、私はいつもその姿を見つめないように注意しながら、心の中でがんばれ、がんばれ、と唱えた。黒目はまっすぐ向けたまま、でも視野の隅の彼女に意識をこらし、どうかメルちゃんが彼女を守ってくれますように、お母さんが彼女を見捨てませんように、彼女が生きることを諦めずにすみますように、と念を送った。
数年前のある朝、駅前のロータリーを歩いていたら突然、彼女とその母親がおしゃべりを交わしながらどこかへ向かって歩く姿が目に飛び込んできた。
二人は、吸い付くような距離感で寄り添い合っていた。しかしその間に以前のような緊迫感はなく、特別楽しそうでも特別険悪でもない代わりに、日常の延長っぽいいそいそした雰囲気が感じられた。
久しぶりに見た彼女を、黒目を動かさずに一瞬観察する。帽子に黒くて長い髪、シナモロールの白いパーカー、斜めがけにした黒とピンクのレスポのウエストバッグ。ミニスカートから伸びた相変わらず細すぎる脚、厚底のサンダル。右手に毛布でくるまれた知らないお世話人形を抱え、首からはピンク色のひもであのメルちゃんを提げていた。メルちゃんにぐっと意識を集中させ、ピンクのひもが赤と黒のチェックのかわいいワンピースについていることを確認する。
すれ違ってから、振り返る。地下鉄の入り口に吸い込まれていく二人を見送り、午前中の清潔な光の中に二人の爽やかさを反芻した。
世の中の多くの人にとって、彼女は「かわいいもの好き」という名前でくくるにはまだまだ異様な姿をしていたと思う。病的にも映ったかもしれない。でも私には、彼女が確かに変化しつつあるのが感じられた。以前よりつややかな長い髪は、彼女が定期的に洗髪をし、外出前にも手入れしていることを物語っていた。調子が悪そうな時は目深になる帽子のつばの角度は浅く、はっきりと目が見えた。人の目が今日は以前ほど気にならないと言うことだろう。親子で足取り軽く、穏やかに何気ない会話を交わしていたことにも心が動いた。
午前中に外出できるようになったのだってすごいことだ。彼女は、外出する何時間が前に起きることができ、そこからメイクをし、髪をとかし、お気に入りのファッションに着替え、荷物をそろえてかばんに入れ、メルちゃんたちの準備を整え、そして外に出てきたのだ。さらにこれから電車に乗るなんて、相当なモチベーションがないとできないはず。
それにしても、メルちゃんを首から提げるなんて最高だよなあ。ピンクのひもは、彼女が自分で縫い付けたのだろうか。ひもつきのお洋服は、彼女のアイデアだろうか? 「お母さん手伝ってよ」とか言って、洋服ごと二人で一緒に作ったものだったりして。
あたたかな光がさす絨毯じきの窓際で、笑いあいながら背中を丸めて手芸をしている二人の姿を勝手に思い浮かべる。私の妄想、いや願望でしかないけれど、もしそんな時間があるのだとしたら、つらく厳しい病いの時期も、二人にとって別の意味を持つ瞬間があるのかもしれないな、と思った。
それから5年あまりが経過したつい先日、駅前の交差点を家に向かって歩いていると、横断歩道の雑踏の中で見覚えのある女性とすれ違った。
一瞬あってから、彼女だ、とひらめく。すぐにわからなかったのは、彼女がそれほどに街の光景に溶け込んでいたからだ。
細い手足は細すぎず、髪の毛は長すぎず、不自然なほど目深に帽子をかぶってもいない。ヒールの高さは相変わらずだったが、色合いも柄もシルエットも記憶に残らないぐらい普通のかわいいファッションに身をまとい、彼女は一人きりでどこかへ出かけていく様子だった。
振り向き、視線を走らせて彼女の姿を探す。黒目で探す。その姿をしっかりと捉えたかった。信号がチカチカと点滅し、赤に変わりそうになる。あわてて駆け出し、映画のワンシーンのように人波をかき分けてみる。しかし、不規則に上下する黒い頭の中に彼女を見つけることはできなかった。
諦めきれずに次の交差点まで歩いてみる。けれど、やっぱりその人の影はどこにもなく、これがマンガなら幻影であってもおかしくないなあ、と思った。あれ以来、彼女のことは見かけていない。
たまにあの日のことを思い出して、本当にあれが彼女であってくれたらいいなと考える。困難な何年間もどうにか命をつなぎ、お母さんやメルちゃんとそのお友達たちと、何でもない今を送ってくれていたらいい。
ご意見、ご感想、ご相談、ご指摘、雑談などあれば、コメントやメールでお寄せください。どうぞみなさま、おだやかな週末を!
bonyari.scope@gmail.com
すでに登録済みの方は こちら